*******************************
MASAMI COLLECTION
******************************
1/10 ツーリングカー Vol.3
**********
1/10 ツーリングカー Vol,2 ← クリック
1/10 ツーリングカー Vol,1 ← クリック
1/10 ツーリングカー PROTO ← クリック
2001年 ツーリングカー 全日本選手権
2001年 MR−4TC SP 2024/02/10MR−4TCのシャーシをナロータイプに変更。

双子のMR4−TC 全日本SPL。 (レプリカ 販売します。)


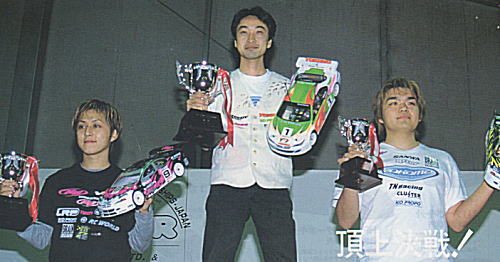

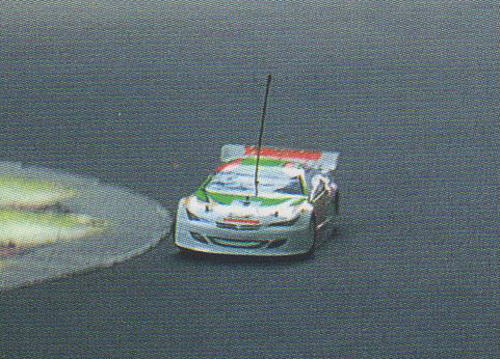
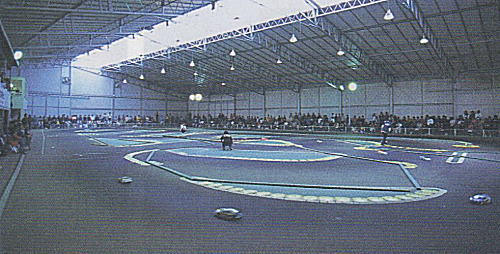
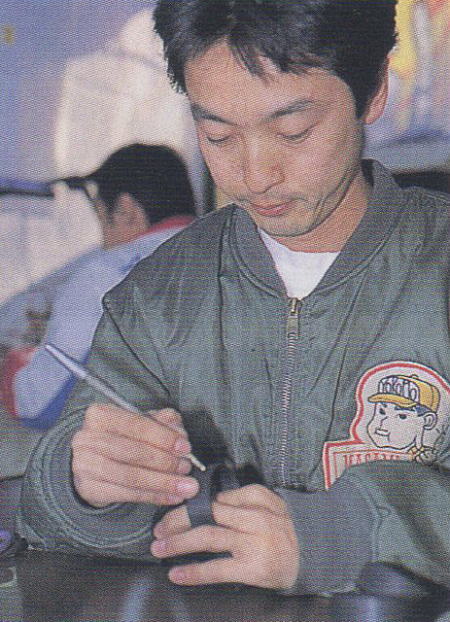
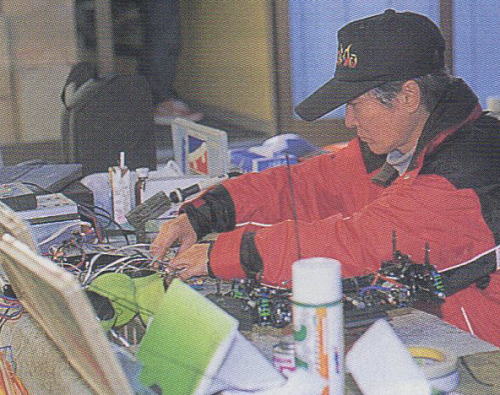
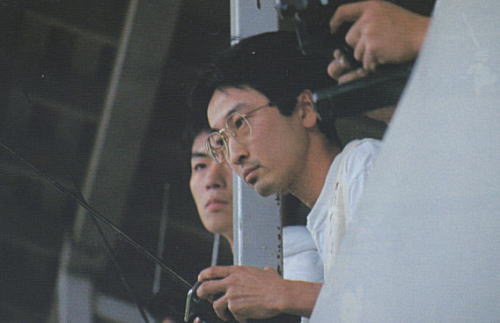
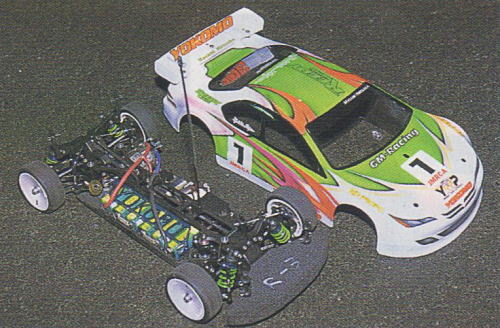
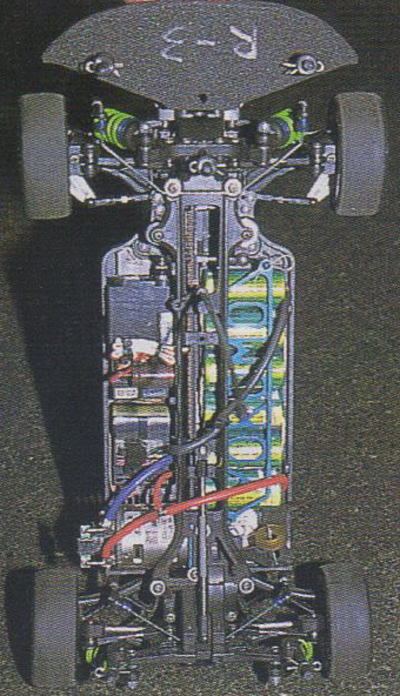

キンブローの樹脂ピニオン使用。
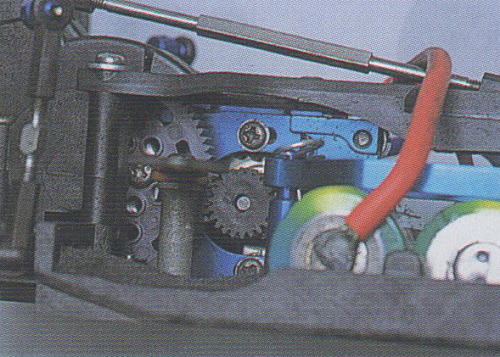
ツニバーサルはアルミ製、シャフトもアルミ
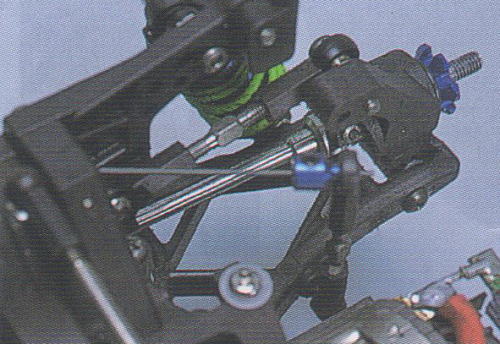
モーターは、REEEDY 8T

バッテリーはヨコモピークマッチド。

1mmトレールのステアリングブロック。


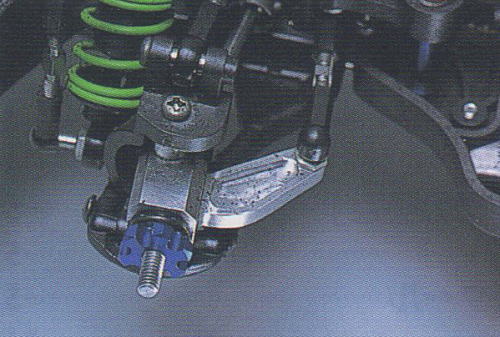
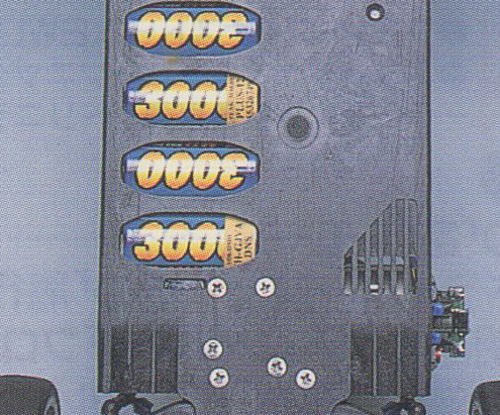
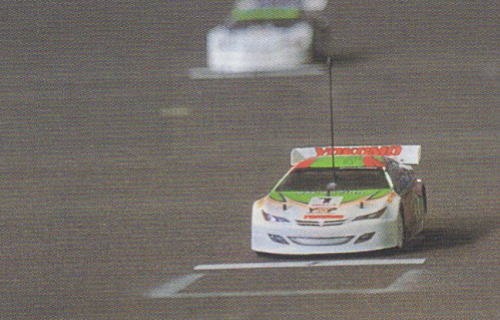

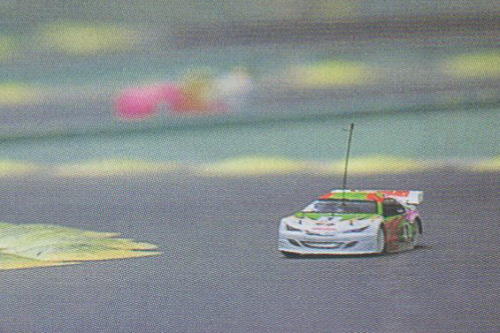









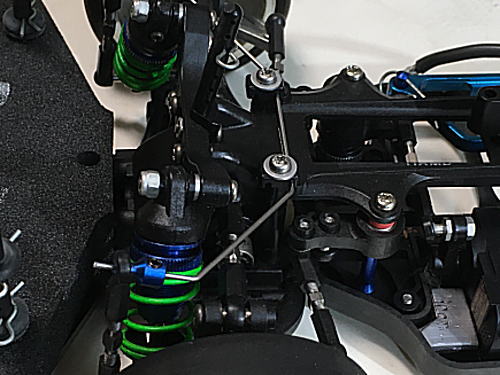

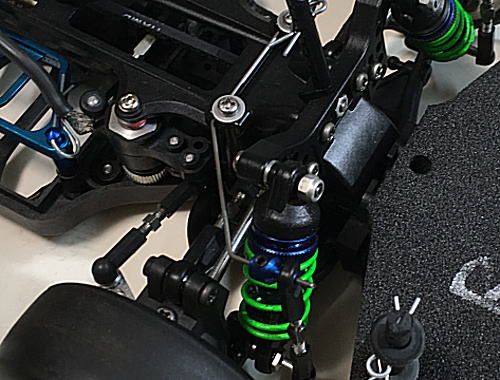
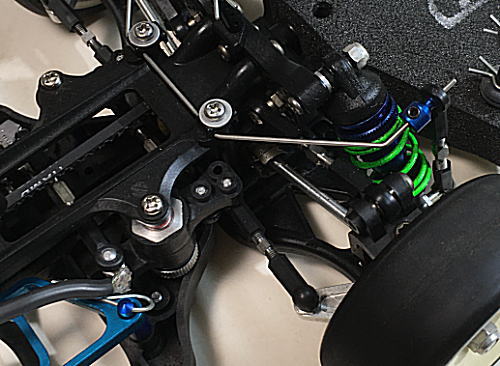
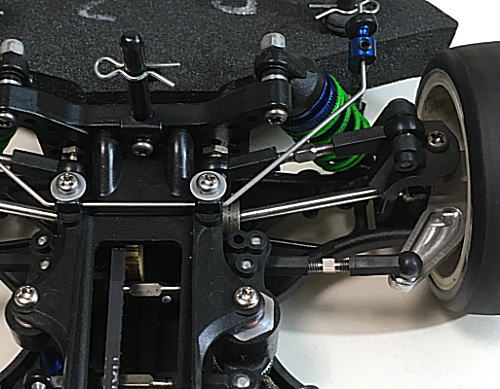
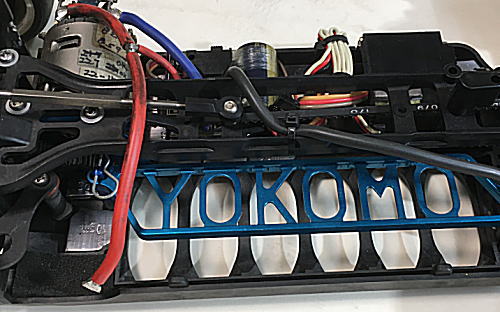

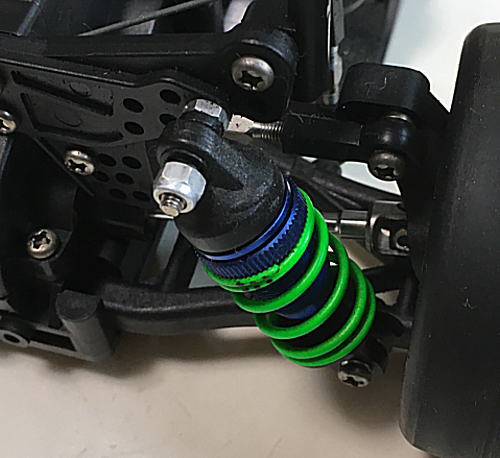
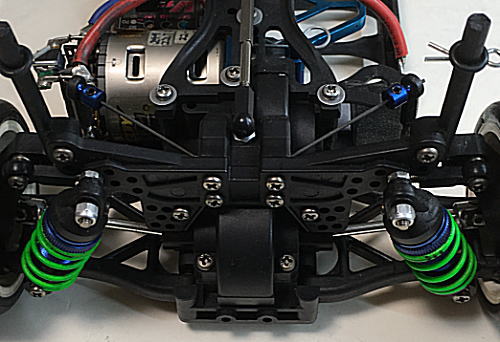
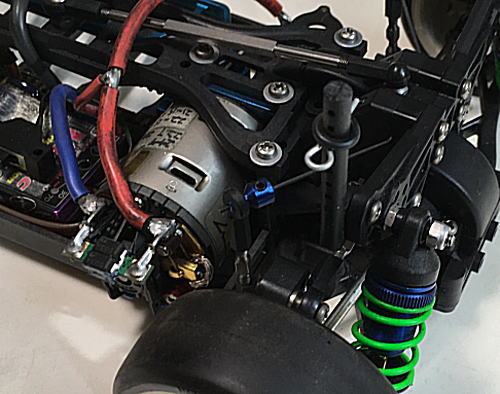

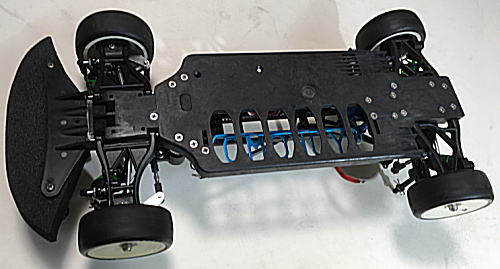

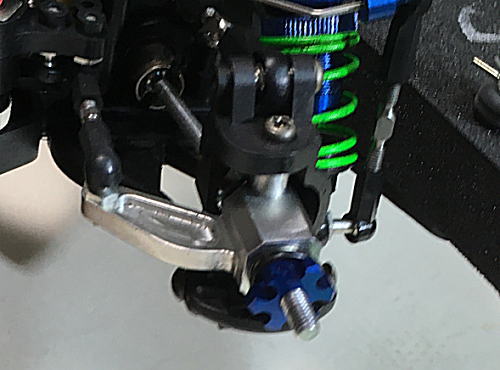
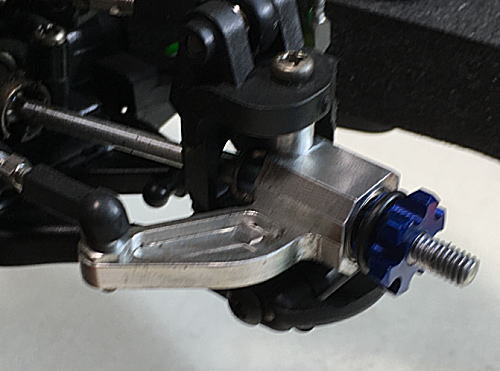
****************************************************
MR−4TC 全日本選手権SPL. レプリカ
レース後、広告及び展示等用に、全く同じ仕様のレプリカを製作しました。
(新品、メカ無し)
このマシン販売します。 価格¥250,000
お問い合わせ info@hirosaka.jp



2001年 スーパーストック選手権
スーパーストック選手権 MR−4 TC SPL. 2024/04/13ストックモーター23Tのみに限定されたレース。 TCはシャーシをナローに。
原篤志選手が、HPIに移籍、今回からメーカー対決をなった。

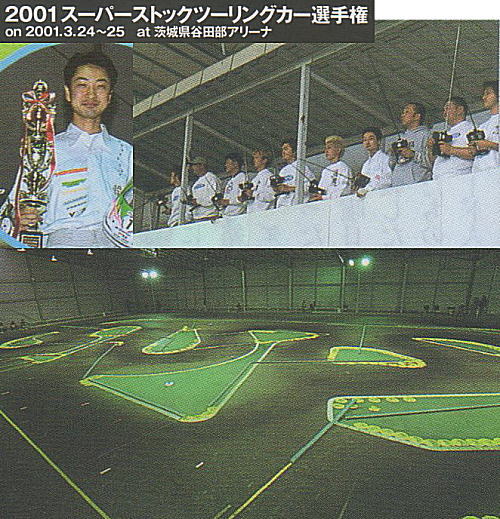
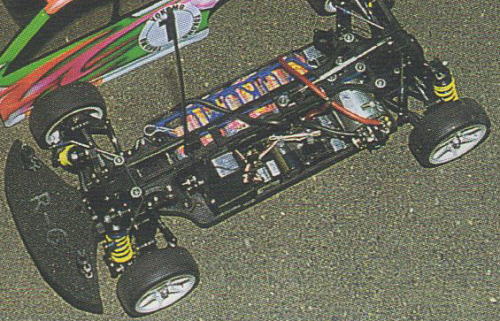

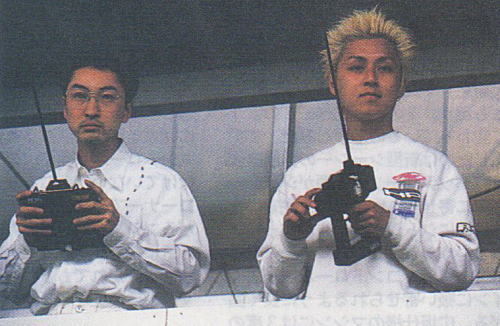

シャーシはナロータイプとなった。
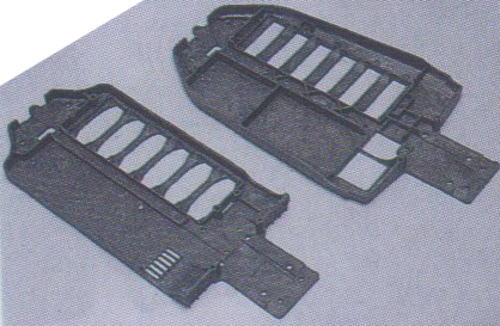
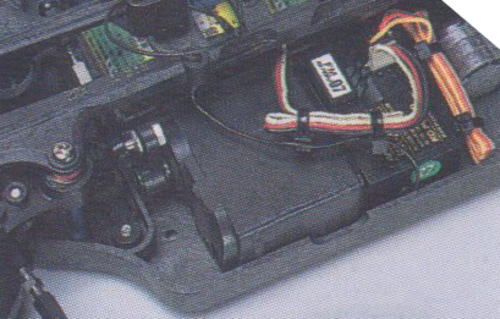
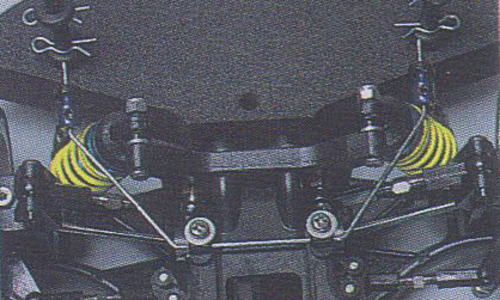

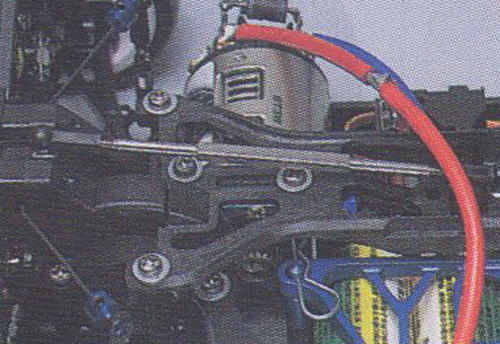
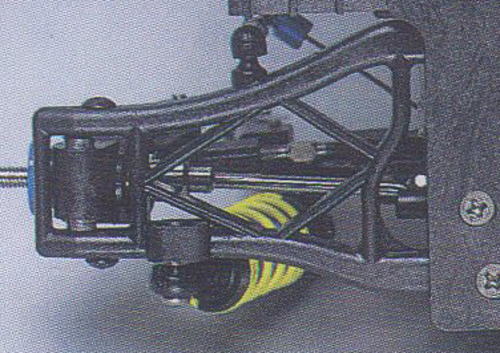
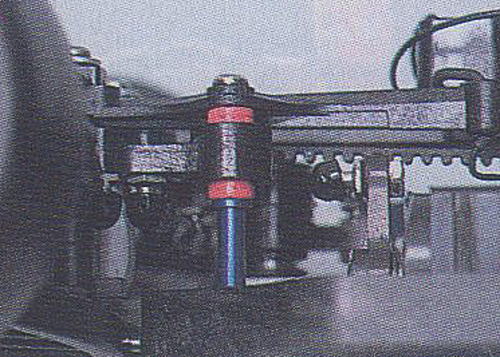
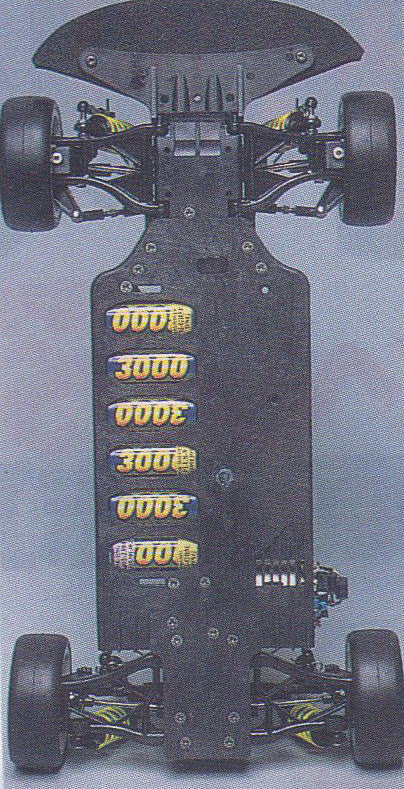
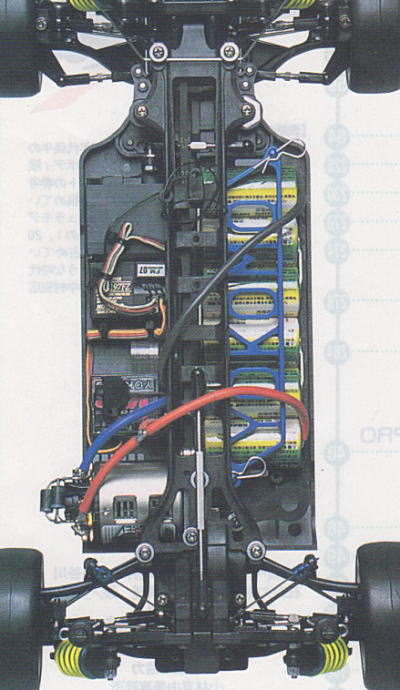
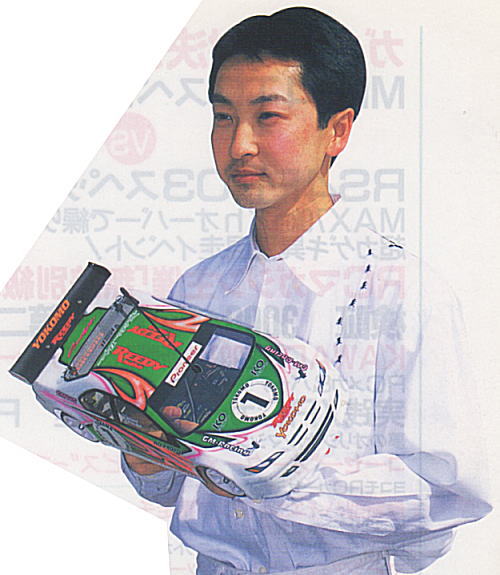



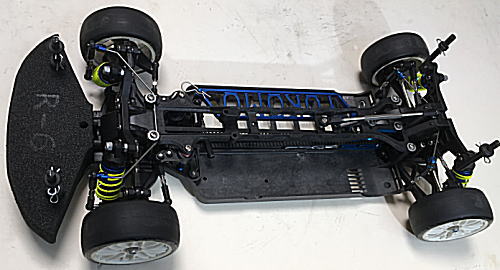
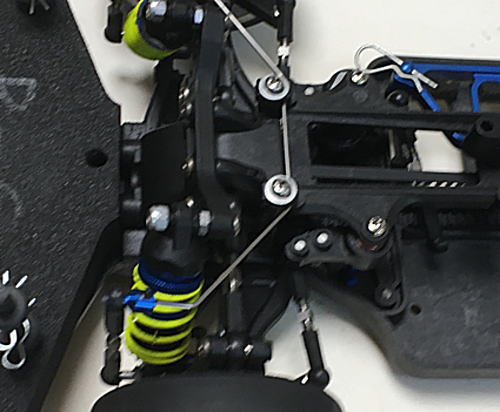
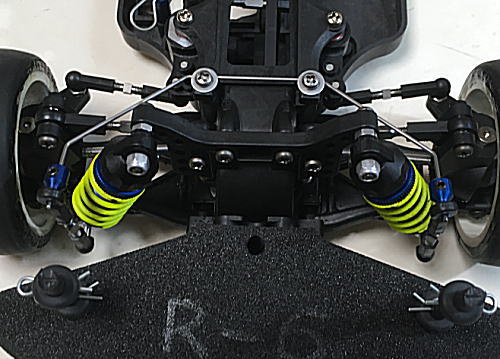

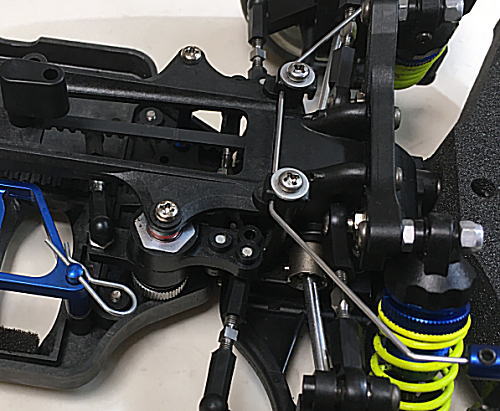
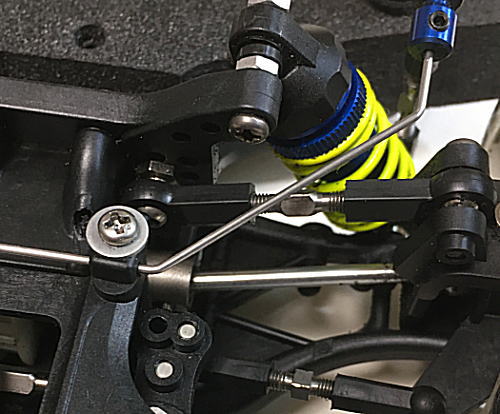
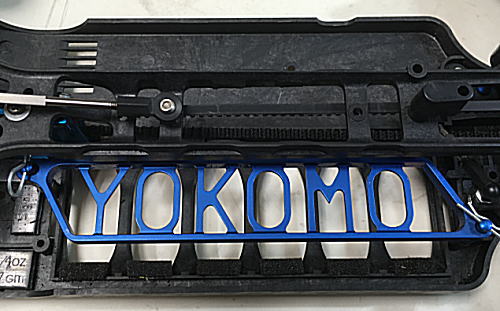
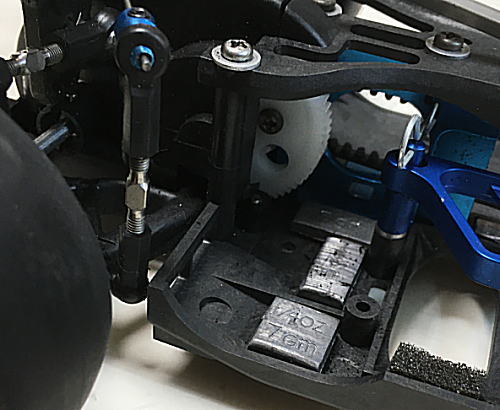
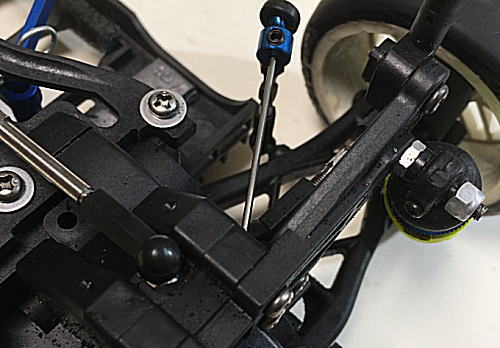
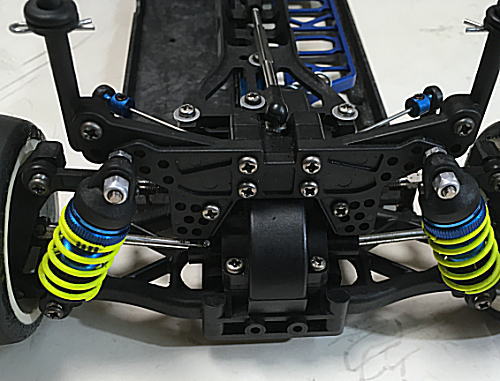
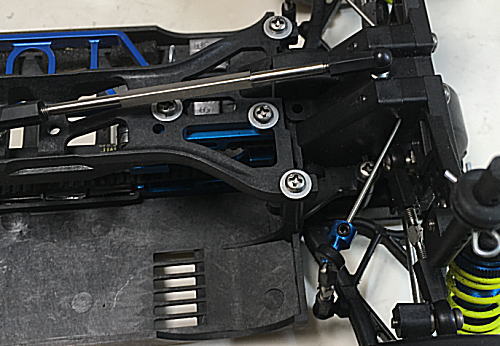

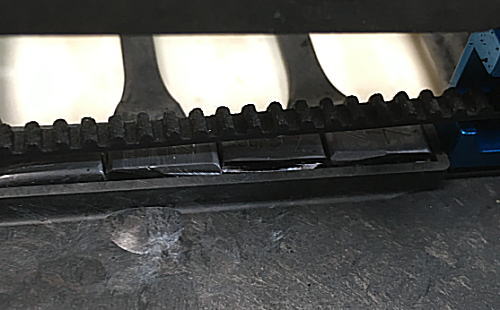
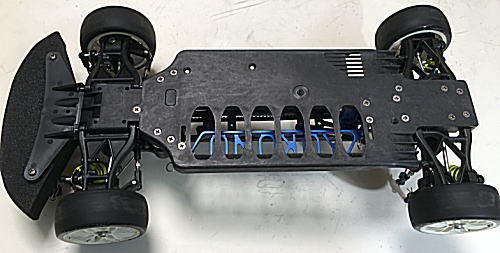

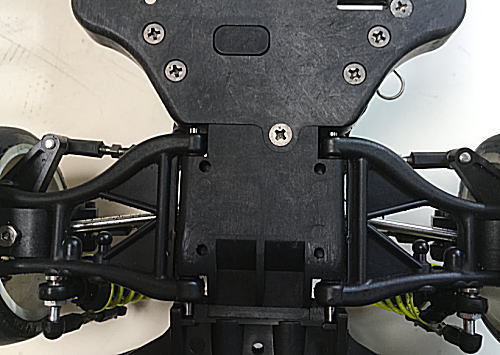
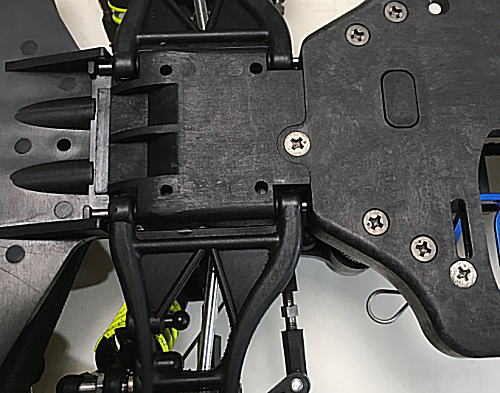
2000年 オンロード 世界選手権 ツーリングカー
2000年 オンロード世界選手権 ツーリングカー 2023/04/17世界選手権最後の種目、ツーリングカー、これまで1/12/1/10共にTQ及び
優勝を獲得し、最後の種目で3種目、パーフェクトを目指し、レースに臨んだが
ツーリングカーはTQは獲得したのもの、決勝レースでは3位に終わった。
しかし正美の後継者と目されていた原篤志選手が優勝し、最良の結果となった。



マシンは、MX−4をベースとした樹脂シャーシのTCW


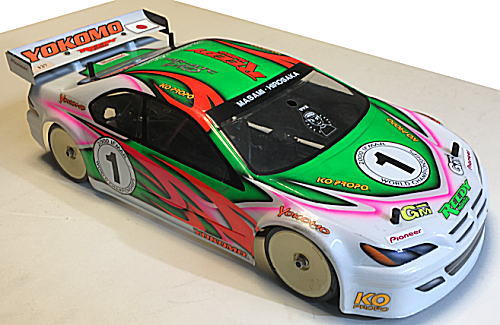




従来のカーボンシャーシに比べ柔らかく、ソフトな走りとなった。
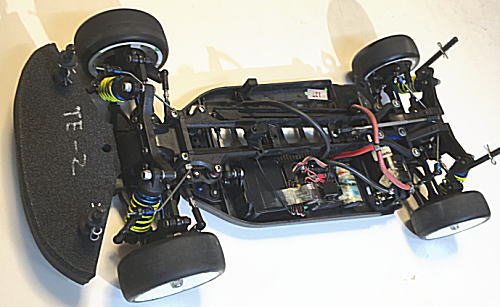
ESCはGM V12 モーターは、REEDY フイリー
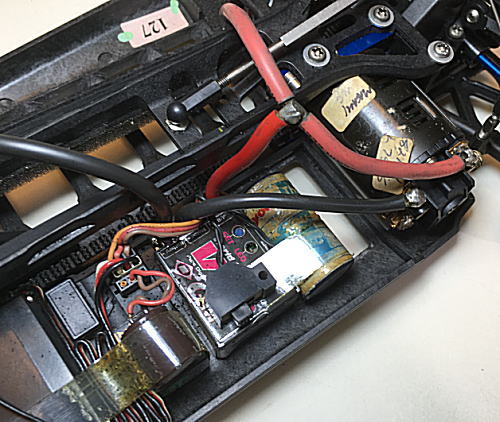

使用車は、テストカー2号車

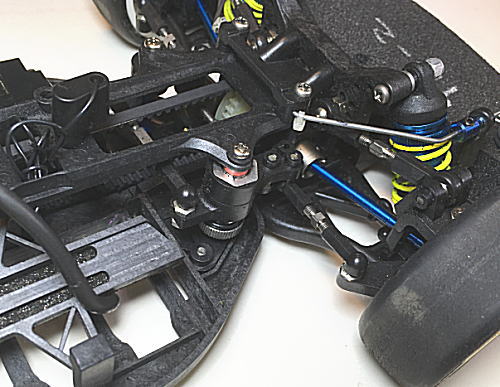
アッパーデッキ後部にテンションロッド、これでベルトの針を調整。
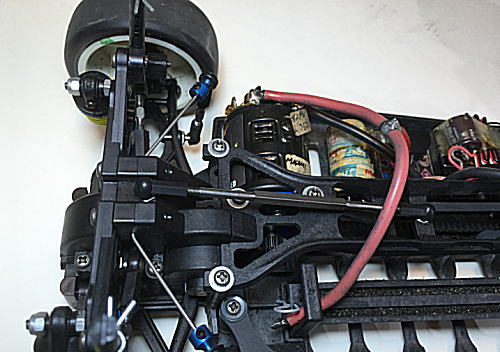
前後スタビを装着
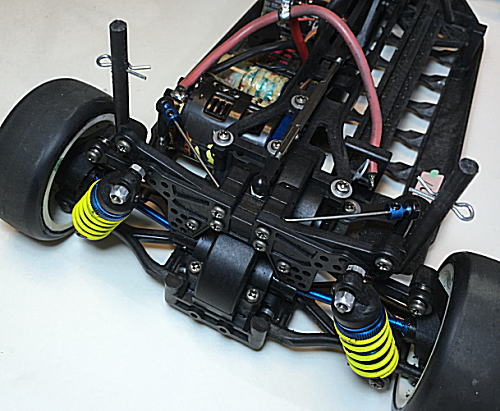

ESCには大きなコンデンサーを使用
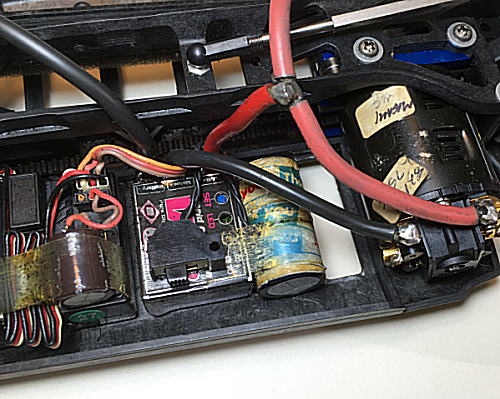
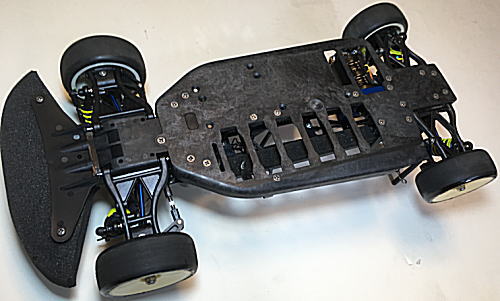


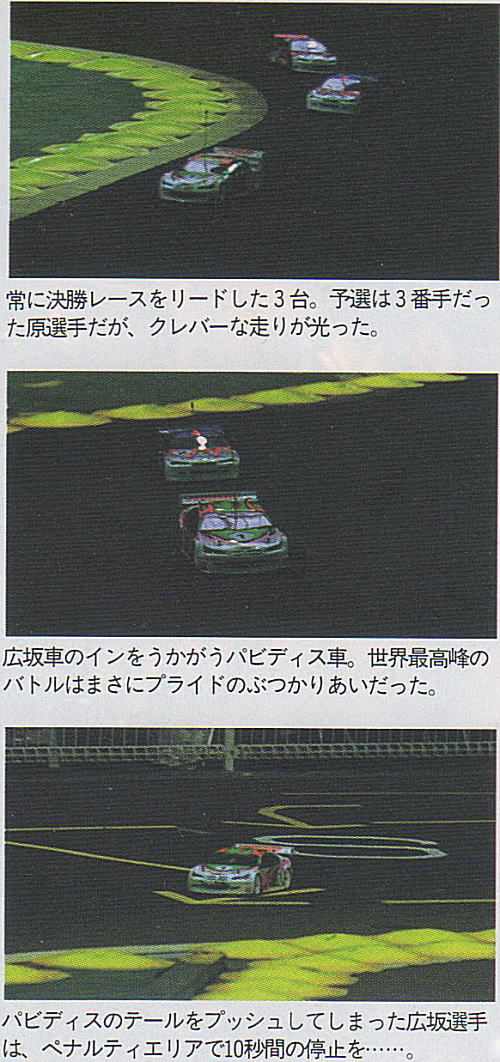
いつもビッグレースは、REEDY氏、正美はビッグレースではREEDY以外は
使用した事は無い。


GMレーシングのラルフ氏 今回はパーフェクト


世界選手権用 プロトタイプ
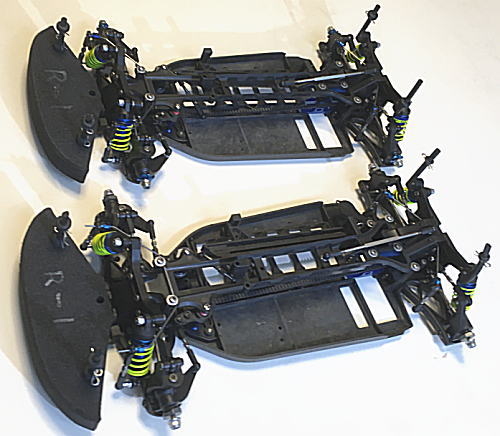

ホイールハブはマグネシウムも用意した。

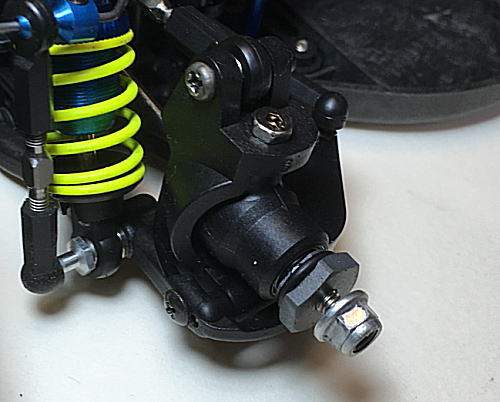
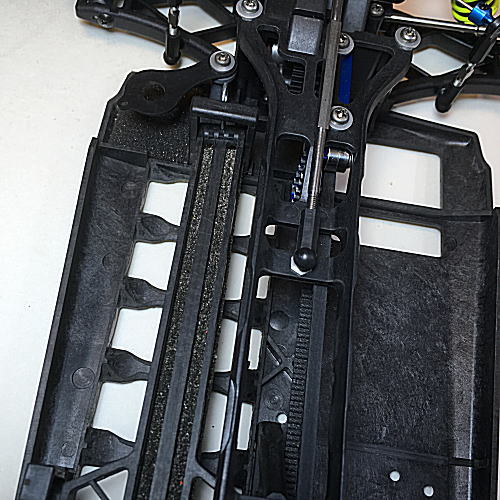
お問い合わせ、ご注文は、 info@hirosaka.jp まで
*******************************************
